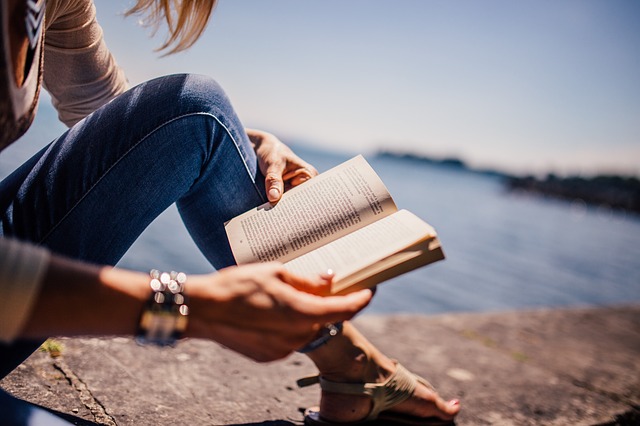駅前開発
この言葉って、地方に住んでいる人は必ず聞く言葉だと思うんです。私が現在住んでいる柏市でも柏駅周辺を開発しようという動きがあります。
商業施設の比率が高いJR柏駅周辺の土地利用を見直し、マンション開発などで住宅の割合を引き上げる。2040年には駅周辺の定住人口を1万7000人と現在のおよそ2倍に増やす目標を掲げる。まちなかに「商住」の機能をバランス良く配し、生活の利便性や街の魅力を高める。
地方になるといかに人を呼ぶかという話題は尽きないので当たり前といえば当たり前ですね。
地元の北柏の駅周辺も開発を現在進行形で行なっていますし(2018年10月現在)
で、今回の話は地方の開発、特に駅前の開発の個性についてです。
「自分の街をどうやったら町おこしできるのか?」というテーマをに興味・関心がある方はぜひ読んでください。
地方の開発、再開発って個性なくない?
正直、地方の開発・再開発って個性がない気がするんです。
マンションやアパートを建てて、デパート等の大型の商業施設(柏の葉ではららぽーとでした)を建てて人とお金の流れを活性化させる。
自分の周りのちょっと人の多い地方都市の開発はすべて同じように見えてしまいました。
開発に携わっている皆様、気を悪くしてしまったらごめんなさい。
もちろん、住宅地と商業施設を作って人の流れとお金の流れを活性化させるのは重要です。でも、それだけだと東京の街をスケールダウンさせただけのように見えてしまうのは自分だけでしょうか?
せっかく地方都市を開発するのであれば、街の特色を生かした形で開発してほしいなと思うわけです。
「逆開発」という発想
そんなことを考えてみると、無印良品のサイトで特集していた「逆開発 ─戻すことで見えてくるもの─」という記事の発想は面白いなと思うわけです。
取り上げている駅は千葉県のローカル線、小湊鐵道(こなみとてつどう)の養老渓谷(ようろうけいこく)駅。読めない笑
ここでは逆開発という開発をしているそうです。
逆開発とは?
逆開発とは駅前のアスファルトをはがし、自然の姿に戻していく開発のことだそうです。
普通、開発というとアスファルトの道路を作り、商業施設など人口の建設物を作るわけですから、まさに「逆」の開発ですね。
小湊鐵道(こなみとてつどう)の養老渓谷(ようろうけいこく)駅の場合
無印良品研究所の記事を抜粋します。
駅前のロータリーを抜けて5分も歩けば豊かな自然があります。渓谷へと向かう遊歩道があり、房総第一の川・養老川に架かる橋へとつながっていく絶好のロケーション。「ある」ものの価値に気づくと、駅と自然との間をアスファルトが遮断していたことにも気づきます。「遮るものを省いていけば、そこにあるものが伝わるのではないか」─そんな考えから、アスファルトを撤去することになりました。
街の特長をじっくり考えると、逆開発をしたほうが良いという判断をしたのですね。自分の街を観察して強みを考えるというのは大切でしょう。
その地に昔から生えていた在来の広葉樹や落葉樹を植え、花の種をまき、約2000m²の駅前広場の敷地を10年がかりで雑木が茂る自然の森に戻していこうというのです。使い古した枕木を敷いたウッドデッキや枕木を積み上げたベンチも設置され、駅舎の前にあったバスロータリーは20m離れた県道沿いに移されました。
自然を森を駅に作るというのは勇気もいるでしょう。しかし、自然を豊かにさせて街の特長を前面に押し出すことで地域特有の産業も生まれるはず。
なぜ商業施設やアスファルト撤廃させるのかまできちんと考えたうえで自然を作っていることがわかります。
逆開発の結果
ていねいに植えられた樹木、その足元には季節の草花、駅舎の並びにある地場産品の販売所には地元の野菜や農家手づくりの梅干し、唐辛子味噌、栗おこわ、草餅などなど。その隣には養老渓谷温泉の湯を引いた「足湯」があり、足を浸してくつろいでいるうちに気持ちよくなってそのまま昼寝する人の姿もありました。
自然豊かな駅になることで新しい商売が始まっていることに注目。商業施設を建てることだけが買いう発ではないということですね。
開発をする上で大切なこと
開発の目的は
- 人が来るようにする
- 人が働ける場所を作る
- お金の流れを生む
の3つがメインでしょう。ということは、自然豊かにしても上記3つが建っ説できればいいわけです。逆に、商業施設を建てても上記の目的が達成できなければ意味がありません。
この逆開発はよくニュースのボイコットで見るような「自然を守れ!」的なものとは違うことが重要です。
ボイコットのような「自然を守れ」は自然を生かして人が来る努力をすることなく放置していては、「何もしないのなら商業施設建てよ?」となります。
「商業施設を建てるのではなく、自然を守って街の特長を残した戦略のほうが町おこし的に良い」と示すことができて初めて逆開発や街の伝統を守る意義が生まれます。
ですから、ぜひ街の特長を整理したうえで、どうやったら街の特長や伝統を活かした開発・町おこしができるのかを考えましょう。